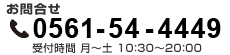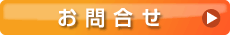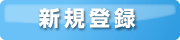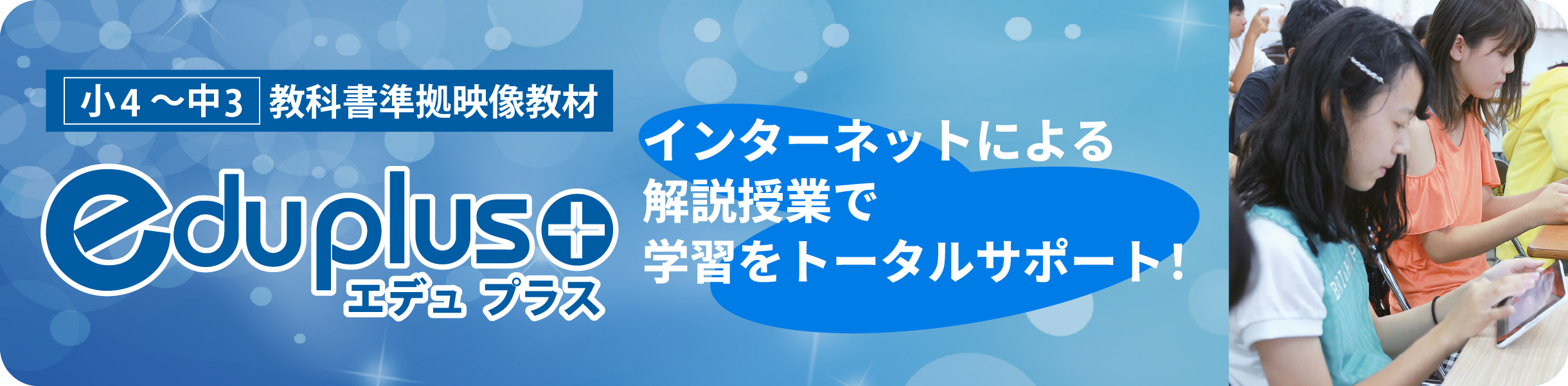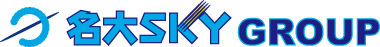新着情報
2025年7月号 小笠原先生の「明日の空(Tomorrow’s sky)に向かって」119
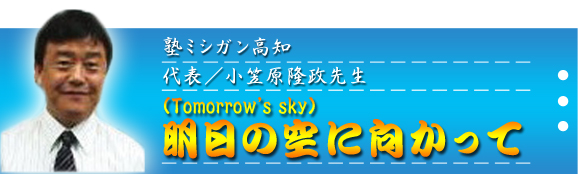
 |
小笠原 隆政(おがさわら たかまさ) <プロフィール> 塾ミシガン高知 代表 ・1985年 米国ミシガン大学の語学理論を用いた英語・英会話教室を開設 不変の語学理論(聴・話・読・書)の応用実践教育を展開 学習時間が自由に選べてキャンセル、変更が自由にできるチケット制を導入 ・2004年 英語教室では大変成果があがり、多くの方に切望されていた総合塾に改編 パソコン教材も導入し、他の科目も語学理論に沿って立体的に応用指導 ・2015年 教室創立30周年名大SKY連載コラム「明日の空に向かって」の執筆開始 教室が英語の四技能を測れるCBT検定の「GTEC」検定会場に認定される 大きな塾よりは自分の目の届く範囲での直接指導塾にこだわって経営している |
映像授業と、生徒たちの未来への想い
5月、有馬常務取締役による「映像授業の失敗する良くない利用法」の研修が各地で開催され、私も参加しました。そこで紹介された内容には、私たち塾仲間が日ごろ話し合っていることが多く含まれており、「自分たちのやり方は間違っていなかった!」と、気持ちを新たにする良い機会となりました。
長きにわたり、名大SKYの映像教材と共に歩んできた私にとって、その恩恵は計り知れません。おかげさまで、公立高校入試の合格率は、この十年以上、途切れることなく100%を維持し続けています。時には、同じように映像授業を活用しながらも、なかなか合格率が伸び悩む塾長先生方から、「一体どのような使い方をされているのですか?」と尋ねられることもありました。そんな時、私は決まって、映像授業が持つ「真の利点」を、改めて問いかけるようにしていました。
映像授業の「真価」とは何か
映像授業の利点とは、一体何でしょうか。それは、何度でも、何度でも、繰り返し学ぶことができる、という点に尽きます。もし夏期講座が朝9時から夜9時まで続いたとしても、映像授業の講師は、決して疲れることなく、一日中変わらぬ熱量で、同じ解説を繰り返してくれます。私たち生身の講師が、同じことをし続けるのは、到底無理な話でしょう。しかし、映像授業には、それが可能なのです。
もうお分かりいただけたでしょうか。映像授業の最も優れた点は、生徒が納得するまで、繰り返し、繰り返し、学ぶ機会を提供できることです。時には「科目によって分かりやすい授業と分かりにくい授業があるように感じるが、どうしたら良いだろうか」と尋ねられることもありました。映像の先生に「もっと分かりやすくしてください」とお願いするわけにはいきませんから、生徒が理解できる範囲を確実に押さえ、そこから先は塾長が補足解説する、これこそが私たちの役割です。
映像授業は、生徒によって理解の度合いが異なるのは当然のこと。むしろ、私はそこにこそ、この教材の真価を見出しました。生徒が「どこでつまずいているのか」を、明確に把握できる。これが、映像授業を使い続けてきた大きな理由です。
例えば数学で「分からない」と訴える生徒には、具体的に「どこの部分から分からないのか」を、はっきりと指摘させます。「解法の3段目の式から4段目の式への変化が分からない」と生徒が言えば、その部分をもう一度、繰り返し見せるのです。何度か見せても理解できない生徒には、いよいよ塾長の出番です。そこで教えてもなお難しいようであれば、一旦、それより難しい問題は置いておき、できる問題を中心に自信をつけさせてあげましょう。逆に、どんどん先に進める生徒には、惜しみなく次の課題を与えれば良いのです。もし、同じ時間に6人の生徒がいて、そのうち3人がつまずいている状況であれば、塾長にとっては確かに大変かもしれません。しかし、だからといって「映像授業は使えない」と一概に決めつける塾長先生が、果たしてどれほど私の実践するような使い方をされているのか、私は知りたいと強く思います。
欲を言えば、塾長の具体的な指導法に関する悩みや質問に、実践的に答えられるような教務的な研修が、この研修に併せてあれば、さらに充実したものになっただろうと感じました。英語に関しては、映像授業が難しいという話をよく耳にします。その授業は予習のためでしょうか、それとも復習のためでしょうか。もしかしたら、理解できる生徒も、そうでない生徒も、全員同じやり方で映像教材に「丸投げ」してはいないでしょうか。それこそ、あまりに無謀なことです。これまでの英語内容をしっかり理解できている生徒には、予習的な授業は良いでしょう。しかし、理解が追いついていない生徒にとっては、まるで「お経」を聞いているかのように、内容が頭に入ってこないかもしれません。概して英語が苦手な生徒は多いと思いますから、学校の授業の復習として映像授業を使う方が、より効果的でしょう。ただし、単語や熟語の基礎ができていない生徒には、事前にそこをしっかり理解させておく必要があります。
受験のその先、生徒たちの人生を見つめる
受験に不合格となる原因は、生徒自身にあるのかもしれません。しかし、志望校を選ばせる私たち塾にも、その一因があるように感じてなりません。「落ちても良いから、とにかく受験したい」と生徒が願うかもしれません。しかし、どの程度の合格率で合格できるのか、長年塾長を務めていらっしゃる方なら、肌で感じていらっしゃることでしょう。生徒がいくら口にしても、不合格になった時のショックは、本人だけでなく保護者の方々にとっても、計り知れないほど大きなものです。私たちもまた、心が痛むばかりです。たとえ幸運にも合格できたとしても、その生徒は下位での合格だったのかもしれません。当然、周りの生徒たちは彼よりも優秀でしょうから、高校入学後、すぐに苦労することになるかもしれません。その時、塾で「その子が続けて塾に来て、高校生の生徒が増えるなら良いではないか」と考える塾長先生とは、私とは根本的に、高校生に対する塾の役割というものが違うように思います。
私は、一度しかない青春真っ只中の彼らの高校時代を、ただ勉強だけで苦労させたくはないと願うのです。クラブ活動に熱中してほしい。生徒会やアルバイトも経験してほしい。さらには、素敵な恋愛も経験してほしいと、心から願っています。若い頃は、良い成績のためには3年間の猛勉強も必要だと考えていましたが、子を持ち、そして孫を持つ歳になり、その考えは大きく変わりました。今では、そんな「親心」で生徒たちを指導しています。
To be continued・・・